業種別AI活用講座
▶ 業務を“設計”し直すための、業種別AI活用講座
小売・製造・ペット業界で培った30年超の実務経験をもとに、
現場で本当に役立つ基礎業務の整備を、藤 崇一郎が監修。
医療・不動産・法曹・製造分野などでのAI活用における豊富な登壇実績を活かし、丁寧にお伝えします。
AIは“構造を整えるための道具”として位置づけ、現場に沿った実務支援を行います。
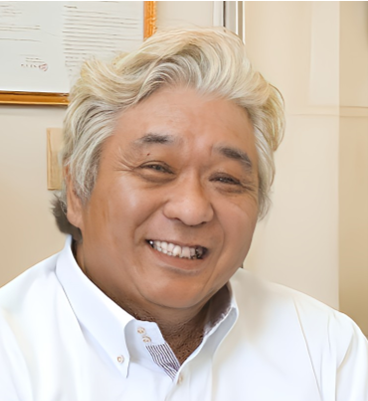
▶ 現場を知り抜いた“実務派”AI講師が監修・指導します

AI活用の第一歩 ─ 飲食・弁当店のためのAI基礎講座
メニュー開発、売上試算と対策、調理・スタッフ教育マニュアル──
現場業務に必要なことを、AIで作成・整理する方法を基礎から教えます。

伝わる売場へ ─ 小売・商店のためのAI活用基礎講座
商品分類、売上対策、粗利試算、ゾーニング設計、企画書作成──
現場業務に必要なことを、AIで作成・整理する方法を基礎から教えます。
▶ 只今開講準備中!しばらくお待ちください。

動物と暮らす ごはんの基礎設計
設計に必要な「嗜好・安全・関係性」の三視点を整理。初学者向け。

犬と人のごはん設計入門
飲食店・OEM向けに、嗜好・安全・関係性の3軸を具体化する実務入門講座。

犬のためが自分のために
犬の健康のために整えたごはんが、自分自身の食生活も見直すきっかけに。

ともに食べるということ
「関係性」からごはんを設計するとは? 家族の食卓から考える講座。
▶ 設計という視点で見直す「ごはんの時間」
「エサではなく、ごはん」。 この言葉にピンときたら、あなたは設計の入り口に立っています。
誰かと食べるという感覚が、そっと戻ってくる──
それはペットの存在がくれた優しい変化かもしれません。
高齢の親や、病後の自分にも優しく届くごはん。それが「わけあうごはん」です。
そして、そのごはんが「保健機能食」としての側面も持ち得る──
栄養学・食品設計の視点からも意味のある構造です。
FANDDFは、「わけあうごはん」を通じて人と動物、社会をつなぐ設計を提案します。

※本講座は、藤 崇一郎が設計・監修。
共食対応フードの栄養設計、行政連携、特許出願など
応用実務に通じた専門家によるカリキュラムで構成されています。
📞 栄養設計やOEMのご相談はこちら


